軽自動車の寿命は「10万km」と言われていましたが、最近では軽自動車の技術が進化し、より長持ちするようになっています。適切にメンテナンスを行うことで、さらに長期間使用することが可能です。
この記事では、軽自動車の寿命や寿命を延ばす方法、そして中古車を選ぶ際のポイントを解説します。
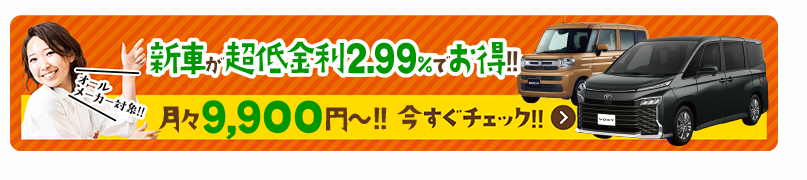

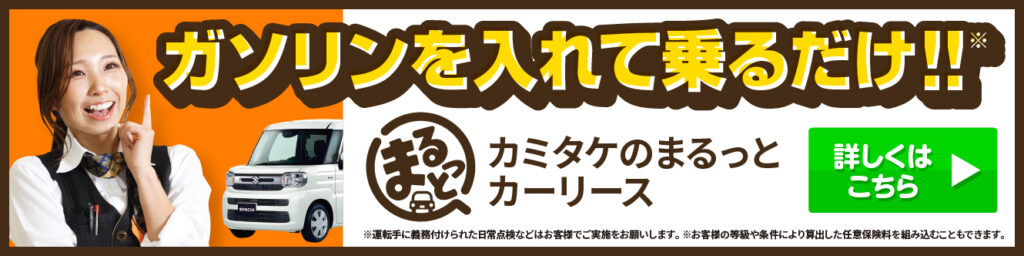
軽自動車の走行距離とは?その重要性と影響

軽自動車の平均走行距離
車は長く走れば走るほど、部品が摩耗したり劣化したりすることが避けられません。そのため、経過年数以上に寿命に影響を与えるのが走行距離です。走行距離が増えると、タイヤなどの消耗品に加えて、マフラー、サスペンションなどの足回り関連部品が故障したり劣化したりします。
一般的には、1年で1万kmの走行距離が目安とされています。年間の走行距離が2万km以上になると、自動車メーカーが定義する「シビアコンディション」に該当し、故障リスクが高くなる場合があります。そのため、注意が必要です。
走行距離が10万kmを超えると故障のリスクが高まると言われています。そのため、軽自動車では、10万km超えの車を買い替えの目安にする方も多いです。しかし、必ずしも10万kmを超えた車を避ける必要はありません。
走行距離が車に与える影響
1年間の走行距離が1万kmが平均、2万kmを超えるとシビアコンディションとよばれます。さらに1年間に3万kmを超える距離を走行すると、過走行車となっていきます。
1年で30,000km以上走っている車と聞くと、「走りすぎているのでは?」と思う方もいるかもしれません。年間の走行距離の目安が1万km程度とされる中では長く感じますが、前のオーナーがきちんとメンテナンスを行っていた車であれば、このような走行距離が多い車でも状態が良好な場合があります。
走行距離が極端に短い場合は注意が必要な一方で、1年間の走行距離が3,000km以下の中古車にも注意が必要です。週末にしか使用しない車や街中での短距離利用が中心の車は、このような走行距離になることがありますが、車検以外のメンテナンスがほとんど行われていない可能性があります。
車は定期的に運転し、メンテナンスを受けることで、良好なコンディションを維持できるため、走行距離が極端に短い車は、状態が悪化している場合も少なくありません。特に、年式が古く走行距離が短い車は長期間放置されている可能性があるため、避けたほうが良いでしょう。
軽自動車の走行距離と中古車市場での価値
中古車を選ぶ際に、気になるポイントの1つは、やはり走行距離です。走行距離が多い車、いわゆる「多走行車」や「過走行車」は、寿命が近いのではないかと心配されることが多く、そのため多くの人ができるだけ走行距離の少ない車を選ぼうとします。そして、この走行距離は車の価格にも影響します。
しかし、低走行車が欲しいけれど予算が厳しい場合や、どうしても欲しい車種が過走行のものしかないという状況もあります。その際、「どの程度の走行距離までが許容範囲なのか」という疑問が生じます。
「10万km」という走行距離は、車の機械部分、特にエンジンやサスペンションといった重要な部品が交換時期を迎える目安です。よく知られているのが、エンジンのタイミングベルトの交換です。タイミングベルトを使用している車では、ほとんどが10万kmまでの交換を推奨されています。
他にも、サスペンションのダンパーやブッシュ類、クラッチディスク、ブレーキローターなども10万kmを超えると交換の必要が出てくることが考えられます。これらの部品の交換は費用がかかるため、事前に確認することが重要です。
そのため、多くの車種で10万kmを超えると中古車の価格が大きく下がることがあります。購入価格が安くなるため魅力的に見えるかもしれませんが、大きな部品交換が必要になる可能性があるため、注意が必要です。
軽自動車の走行距離を延ばすためのメンテナンス方法

定期的にオイル交換する
エンジンオイルは、車にとって非常に重要な役割を果たしています。エンジン内部で金属同士の摩擦を減らし、車がスムーズに走行できるようにする潤滑剤のような働きをしています。そのため、エンジンオイルの管理は欠かせません。
交換時期としては、少なくとも1年に1回の交換が目安です。また、走行距離に基づいて判断する場合は、1万km走行した時点で交換を行うとよいでしょう。ただし、山道や高速道路を頻繁に走行するなど、車に負担がかかる運転が多い場合には、5,000km走行した時点で交換を検討するのが理想です。
※カミタケモータースでは4,000kmまたは6か月に一度の交換をおすすめしています。
ATフルード/CVTフルードも交換する
AT車やCVT車に乗っている場合、フルードの交換は重要です。定期的にフルードを交換することで、エンジンの力がしっかりとタイヤに伝わり、スムーズな走行が可能になります。交換を怠ると、最悪の場合、エンジンが故障してしまう可能性もあります。
交換の目安はメーカーや車種によって異なりますが、フルードは全てを一度に抜き取るわけではなく、新しいものを補充しながら古いものを少しずつ抜いていきます。そのため、完全に劣化してから交換すると新しいフルードが多く必要となり、費用がかさむ場合があります。
ATなら20,000kmに1回、または2年に1回、CVTなら40,000kmに1回、を目安に交換することで、費用を抑えながら車の良好な状態を維持できるでしょう。交換費用は5,000円から30,000円程度と幅が広くなっています。
タイヤのチェックとメンテナンス
タイヤも重要な消耗品の1つです。タイヤの状態が悪くなると、車全体のパフォーマンスに影響を与えるだけでなく、エンジンに余分な負担がかかることがあり、さらに安全性も低下するため危険です。
タイヤ交換のタイミングは、タイヤの溝が1.6mm以下になったときが目安です。溝が減るとスリップサインが出てきますが、これが見えたらすぐに交換を検討すべきです。スリップサインが出た状態で走行することは、道路交通法違反になる可能性があります。
新品タイヤの溝は約8mmで、通常5,000km走行ごとに1mmずつ減っていくとされています。溝が残っていてもタイヤが硬化してしまうとブレーキの効きが悪くなるため、こちらも交換のサインとなります。メーカー推奨の交換期限は4〜5年ですので、それを目安に交換を検討すると良いでしょう。
バッテリーやエンジンのメンテナンスをする
タイミングベルトはエンジンの回転を支える重要な部品で、ゴム製ですが耐熱性や耐久性が強化されています。ただし、劣化が進むとエンジンが正常に回転しなくなり、最悪の場合はエンジンが止まってしまうことがあります。タイミングベルトの交換目安は10万kmですが、走行距離が少なくても定期的に状態を確認しておくことが重要です。
タイミングベルトに限らず、エンジンオイルやブレーキパッド、バッテリーなどのメンテナンスも日頃から行うことで、車のコンディションを保つことができます。車を長持ちさせるためには、日々のメンテナンスが重要です。
可能なら屋根付の駐車場に保管する
車の寿命を延ばしたいなら、屋根付きの駐車場に駐車するのはおすすめです。どうしても青空駐車をすると、塗装面に紫外線の影響が出てしまうことがあります。
屋根の下で保管しているなら、塗装のよい状態を保てます。状況によって駐車環境は異なりますが、よりよい塗装状態をキープするためには、屋根付の駐車場に駐車するようにしましょう。
運転方法に気を配る
急にブレーキをかけたり、急発進をすると、エンジンが高回転し、部品に過度な負担がかかってしまいます。これを繰り返すと、車の寿命が短くなる原因にもなり得ます。
できるだけスムーズでエコな運転を心がけることで、エンジンやその他の部品に負担がかかりにくくなり、車の長寿命化につながります。
軽自動車の走行距離が多い場合の購入時の注意点

過走行車のデメリット
売却時に値段がつかないかもしれない
車の価値は、年式や走行距離、さらには市場での人気などさまざまな要素で決まりますが、特に走行距離は重要なポイントです。過走行車は市場での価値が低いため、売却時にほとんど値がつかないことがあります。高年式の車でも、走行距離が伸びると価値がどんどん下がり、10万kmを超えた時点でほぼ価値がなくなることが多いです。
購入時に安く手に入る場合もありますが、売却時の価格についてはあまり期待しないほうが良いでしょう。
見た目が悪い場合もある
高年式の過走行車は、短期間で多く使用されていることが多く、小さな傷や落ちない汚れが目立つことがあります。車は使用するほどにどうしても傷がつき、汚れていきますので、綺麗な状態を求める場合は、購入後に外装のメンテナンスが必要になるかもしれません。
軽い傷であれば自分で修理することも可能ですが、手間がかかりますし、業者に依頼すると費用が高くなる場合があります。見た目を重視する方には、過走行車は避けたほうが無難かもしれません。
購入前に確認すべきポイント
過走行車は整備記録をチェック
軽自動車で走行距離が10万kmを超えている中古車は、基本的にはあまりおすすめできません。しかし、例外も存在します。それは、高年式の多走行車です。
高年式の多走行車とは、主に経過年数は少なく長距離を走っている車両のことを指します。例えば、毎日通勤で片道50km、往復100kmの距離を走行している車両ですと、1年で2.4万kmも走行することになります。
このような車両は、メンテナンスがしっかりと行われていることが多く、高速道路を主に走っているため、ストップ&ゴーが少なく、エンジンやブレーキにかかる負担も少ないと考えられます。年式が新しく、走行距離が多いだけであれば、状態が良い車両も多く存在します。
定期的に部品交換されているならおすすめ
定期的にメンテナンスがしっかりと行われている車両はおすすめです。車検や法定点検の際に必要な部品交換がきちんと行われており、特に10万kmのタイミングで適切な整備がされている車両であれば、まだ十分に使用できる可能性が高いです。整備記録がしっかりと残っていて、確実にメンテナンスが実施されていることが確認できれば、掘り出し物である可能性も高いです。
一般的に、軽自動車やコンパクトカーは10万kmを超えると中古車市場での人気が急激に落ちます。状態の悪い車両やメンテナンスが必要な車両は、多くの場合、廃車や輸出に回されるため、市場に出回ることは少なくなります。ただし、販売店が状態の良い多走行車を下取りし、そのまま販売するケースも見られます。こういった車両は、掘り出し物として注目すべきでしょう。
長持ちさせるための追加メンテナンス
車の寿命については、「どのくらいの年数や走行距離まで使用できるか」という点が気になるところです。一般的には、性能が落ち始めるタイミングが年数で15〜20年、走行距離で15万〜20万㎞と言われています。特に普通車の場合は、このような目安がよく見られます。
一方で、軽自動車は普通車よりもやや耐久性が低いとされており、寿命の目安は12年、12万㎞程度です。
「車が寿命を迎える」とは、部品を交換しても他の部品が次々と故障し始めるような状態に陥ることを指します。
しかし、愛車をできるだけ長く乗り続けたい場合は、定期的なメンテナンスが重要です。定期的なメンテナンスを行うことで、車の状態を良好に保つことができ、結果として寿命を延ばすことが可能です。
さらに、メンテナンスがしっかり行われている車は、売却する際にも査定額が高くなる傾向があります。
- タイミングベルト:10万km
- ウォーターポンプ:10万km
- ラジエータホース:10万km・10年
- オルタネーター:10~15万km
走行距離が上記に達したのであれば、予防整備しておくことを検討しましょう。
保証の内容をチェック
中古車を購入する際、保証が付いていないものは選ばない方がよいです。また、中身が不十分な保証も同様に避けるべきです。しっかりとした内容で、かつ長期間の保証を付けることが大切です。
その理由は、保証にかかる費用よりも、万が一故障した場合の修理費用が大きくなることが多いからです。特に、安価な中古車に手厚い保証を付けて購入することで、コストパフォーマンスが大幅に向上します。
新車でさえ、保証が付いているのは、新車でも故障が起こることがあるためです。車は年式が古くなるほど、また走行距離が長くなるほど故障のリスクが高まるのは言うまでもありません。そのため、10万キロを走行した中古車に保証を付けないのは、リスクの高い選択だと考えられます。
したがって、走行距離10万キロ前後の安価な中古車こそ、有料であったとしても手厚い保証を付けて購入するべきです。保証なしの激安車を購入したり、手厚い保証が付けられるプランがあるにもかかわらず、それを選ばなかった結果、故障時に高額な修理代を自己負担することになり、後悔してしまうのです。
「今の車は10万キロを走ってもそう簡単に壊れないのではないか」と考える方もいるかもしれませんが、特に電気系統のトラブルは突然発生します。たとえば、エンジンのセンサーが故障してエンジンが停止したり、パワースライドドアのモーターが壊れてドアが閉まらなくなることがあります。家電やスマートフォンが突然壊れるように、電気系の問題は予兆なしに発生します。
エンジンやオートマチックトランスミッションなど、走行に影響を与える部分が故障した場合、修理しなければ車を使用し続けることはできません。たとえば、エンジンの修理に35万円、オートマチックトランスミッションの修理に25万円、パワースライドドアの修理に15万円かかることがあります。これらの修理をしなければ、車に乗り続けることは難しいでしょう。
その結果、安く購入したつもりが、修理費が嵩み、最終的には高額な支払いをすることになってしまいます。年式が古い車の場合には、コンディションの確認はもちろんのこと、保証内容のチェックも必要です。
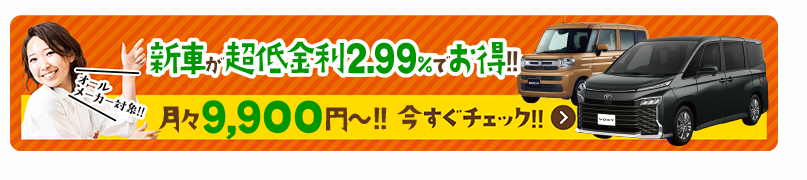
走行距離が延びた車の注意ポイント
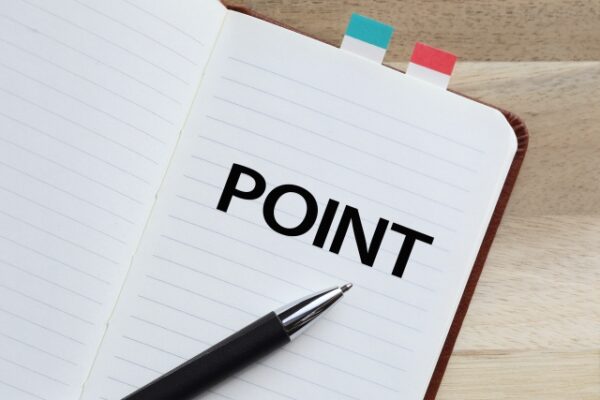
13年目から軽自動車税がアップする
車を所有している方は、毎年4月1日時点で車を保有していると自動車税を支払う必要があります。特に注意したいのは、車が13年目を迎えると、自動車税が上がることです。
増税される理由は、13年以上経過した車は排出ガスが増加し、環境に対して悪影響を与える可能性が高くなるためです。また、古い車は新しい車に比べて安全装備が少ないこともあり、税金を上げることで買い替えを促進し、安全運転を支援する意図もあります。
自動車税は車の用途や排気量によって金額が変わりますが、「自家用乗用車」と「軽自動車」に分けられます。普通乗用車は排気量に応じて税額が変わりますが、軽自動車の場合は税額が一律です。
さらに、初年度検査の時期によっても税額に差が出るため、確認しておくことが重要です。
平成27年3月31日以前に初回検査を受けた軽自動車の場合
- 13年未満:7,200円
- 13年目以降:12,900円
平成27年3月31日以降に初回検査を受けた軽自動車の場合
- 13年未満:10,800円
- 13年目以降:12,900円
平成27年3月31日以前の車では、13年目以降の税金が5,700円上がります。それ以降に検査された車でも、差額は2,100円ですので、注意が必要です。
新車登録から13年が経過すると、毎年このような増額が発生しますので、古い車を所有している方は特に注意しておくとよいでしょう。
安全性能が古いものになる
安全技術の進化です。この10年で、自動ブレーキやエアバッグなどの安全技術が大きく進歩しました。自動ブレーキは、歩行者の飛び出しやドライバーの注意不足でブレーキが遅れた際に、自動でブレーキをかけてくれるシステムです。また、エアバッグも運転席や助手席だけでなく、後部座席にも標準装備されるようになっています。
古い車は、新しい車に比べて最新の安全技術が少ないことが多いです。今後さらに安全技術が進化し、義務化されるものも出てくるかもしれません。そのため、古い車に乗る場合は、新しい車以上に安全に注意して運転する必要があります。
燃費が悪くなる
古い車を長く乗り続けると、燃費が悪化することに注意が必要です。特に最近の車は、ハイブリッド車をはじめとして、どんどん燃費が向上しています。
軽自動車でも、ダイハツのミライースはWLTCモード25.0km/L、スズキのアルトは27.7km/Lと低燃費です。
一方で、古い車は経年劣化により、エンジン内部の部品が摩耗し、抵抗が大きくなります。その結果、燃費が悪化してしまいます。もし、燃費が悪くなったと感じたら、燃費の良い車に買い替えるという選択肢もあります。購入費用がかかるかもしれませんが、長期的に見るとガソリン代の節約につながり、結果的にはお得になることもあります。
たとえば、現在の車が燃費10km/Lだとして、燃費25km/Lの車に買い替えた場合を考えます。1年間で10,000km走行する場合、燃費30km/Lの車では年間で400Lのガソリンを消費しますが、10km/Lの車では1,000Lです。その差は600Lに達します。ガソリン1Lを160円とすると、年間で96,0000円もの差が生じます。
ハイブリッドカーであれば古くても燃費がよいこともありますが、基本的に新しい車の方が燃費性能が優れているので考慮するとよいでしょう。
まとめ
軽自動車は寿命を判断する要素として、走行距離が気になります。以前は10万kmを走行したなら寿命というイメージでしたが、今ではメンテナンス次第でさらに乗ることができます。もちろんコンディションやメンテナンスにかかる費用を計算して判断する必要はあるでしょう。それでも以前ほど走行距離が寿命を判断する基準ではありません。




よくある質問
- 走行距離が多い軽自動車は避けるべき?
-
走行距離が多い軽自動車は、車両のコンディションをチェックしておくべきでしょう。低年式で走行距離が多い軽自動車であれば、メンテナンスもしっかりされている場合もあり、車両のコンディションがよいこともあるでしょう。
- 中古の軽自動車、走行距離と年式どちらを優先すべき?
-
どちらもチェックしておく必要があります。距離が短くても年式が古いモデルであれば、予想以上に車両の状態が悪いこともあります。一方で走行距離が多く、年式が古くても定期的にメンテナンスや部品交換されている車両であれば、コンディションがよい場合もあるでしょう。
- 走行距離に影響を与える運転習慣とは?
-
急ブレーキや急ハンドル、急アクセルが習慣になっていると走行距離の割にコンディションが悪くなるケースがあります。

