車の整備を仕事とするには、国家資格である自動車整備士の資格を取得する必要があります。専門的な資格と感じることがありますが、事前に学習しておくなら、必ずしも難しいものではありません。
一口に自動車整備士といっても、実は一級から三級まで違いがあります。そもそも自動車整備士とはどのような資格でしょうか?資格取得に必要な点やキャリアプランについても解説します。

カミタケモータースでの仕事内容も説明します。
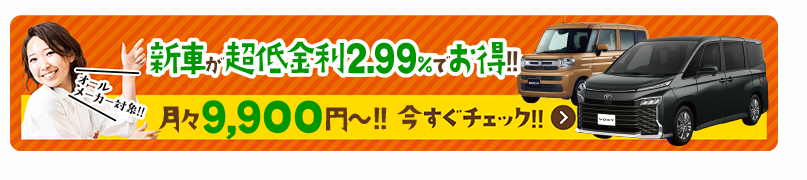

自動車整備士資格とは?

自動車整備士資格の概要
自動車整備士は、車の専門家になるための大事な資格です。自動車整備は、無資格でもできますが、しかし国家資格を取得しているなら仕事の幅が広がります。
タイヤの脱着やオイル交換など、専門的な知識がなくてもできる作業内容なら無資格でも可能ですが、エンジン分解や点検整備など、分解整備は資格がなければできません。
有資格者と無資格者ではできる業務が異なるので、一人前の整備士として働くのであれば、やはり資格は必要です。
特にハイブリッドカーなどが登場して、複雑な整備が求められるようになり、整備士の資格は必要となっています。
資格の重要性と必要性
車は日常的に使いますが、何もしなくてもよい訳ではなく定期的なメンテナンスが必要です。そのために点検や車検、消耗部品の交換を行うものです。
これらの作業を行うために自動車整備士の資格が必要となります。異音や不具合の状況から交換が必要な部品を特定し、必要な部品交換や整備を行います。
整備士が的確に判断して、手際よく修理することで、安心できるカーライフを送るのです。自動車が身近になっているからこそ、資格を持っている整備士の存在は大切です。
既述したように、無資格で行える作業もありますが、分解整備になると資格が必要となります。整備士として働くのであれば、資格取得を目標にしましょう。
自動車整備士資格の種類

自動車整備や点検に必要な資格と主な特徴を見ていきます。それぞれの資格によってできる作業や難易度が異なっています。
1級自動車整備士
- 1級大型自動車整備士
- 1級小型自動車整備士
- 1級二輪自動車整備士
1級自動車整備士は、整備士の資格の中で上位の資格で、合格率も低くなっています。取得の難易度が高く、整備士で取得している方も多くはありません。
一般的な車の整備であれば、2級自動車整備士の資格があれば従事できるので、一級を取得している方が少なくなっています。それでもハイブリッドや電気自動車が増えてきているので、有資格者として作業できる1級自動車整備士の重要性は高くなっています。
2級自動車整備士
- 2級ガソリン自動車整備士
- 2級ジーゼル自動車整備士
- 2級自動車シャシ整備士
- 2級二輪自動車整備士
2級自動車整備士は、一般的な整備作業を行える資格です。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンで動く自動車の一般的な整備を行うのに必要な資格です。非常に高度な作業以外はほとんどの整備を行えます。
3級自動車整備士
- 3級自動車シャシ整備士
- 3級自動車ガソリン・エンジン整備士
- 3級自動車ジーゼル・エンジン整備士
- 3級二輪自動車整備士
3級自動車整備士は、基本的な整備を行うための資格です。ボディやエンジンを除いた部分の整備なので、作業できる範囲が限られています。整備士として最初の作業を行うための資格です。一般的には、その後2級自動車整備士を目指します。
自動車検査員
自動車検査員は、車の整備ではなく整備後の検査をするための資格です。車を整備する人がいるなら、車検のように整備されており、保安基準を満たしているかチェックする人も必要です。
整備工場によっては整備から検査業務まで行うことがありますが、同じ人が整備から検査までできる訳ではありません。この自動車検査員の資格を持っている人がテスターなどを用いて保安基準を満たしているかの確認を行います。
特殊整備士
特殊整備士には、以下のものがあります。
- 自動車タイヤ整備士
- 自動車電気装置整備士
- 自動車車体整備士
特殊整備士は、特定の車種やパーツに特化した整備を行う専門家に必要な資格です。
自動車タイヤ整備士
タイヤの点検や修理、さらに整備を行うための資格です。平成12年まで実施されており、現時点では国家試験は行われていない資格です。タイヤのスペシャリストで修理や点検を行うための国家資格で、知識や技術があることを証明できるので業務の幅が広がるでしょう。
自動車電気装置整備士
自動車電機装置整備士は、車の電気に関係する部分の点検や修理、さらに整備を行うためのスペシャリストです。バッテリーや電子制御装置など、電気に関わる部品が多数使用されていますが、電気装置に関する知識や技術を証明できる資格です。
自動車車体整備士
自動車車体整備士は、フレームやボディの点検や修理、整備を行うための技術があることを証明できる資格です。
板金塗装は資格がなくても業務を行えるものですが、特に車体に関する知識があることを資格の形で証明できるなら、お客様に見せて安心感を与えることができるでしょう。板金塗装をメインで行っていくなら取得しておきたい資格です。
自動車整備士資格の取得方法

資格取得の流れ
ガソリン整備士やジーゼル整備士の受験資格は以下の通りです。
受験資格(必要な実務経験や学歴)
ガソリン整備士・ジーゼル整備士
| 卒業した学校の種類 | 実務経験 |
| 自動車整備系や機械工学科以外の学校を卒業 | 3級取得後3年以上 |
| 機械工学科等の高校や整備士3級課程の高校・専門学校等を卒業 | 3級取得後2年以上 |
| 機械工学科等を卒業(大学、高等専門学校) | 3級取得後1年6ヶ月以上 |
| 養成施設(専門学校)、認定大学等を卒業(2級整備士課程) | 卒業と同時 |
資格を取得するには、複数のステップを踏む必要があります。まずは専門学校などで学ぶ必要があります。
整備技術について知識を蓄えるだけでなく、実際の作業に必要な技術についても学びます。資格を持たない状態から取得を目指すこともできますが、整備工場などで実務経験を積んでから、三級の資格を取得を目指すことになります。
しかし実務経験が求められる年数が増えるため、一般的には専門学校に通うことが近道です。別の方法として、大学に行く場合もあるでしょう。
このようにして必要な知識を得られる、何らかの学校・大学に通います。さらに必要な実務経験の年数を満たす必要があります。
既述したように、専門学校や大学を卒業したなら、同時に受験資格があるので最短ルートです。
試験内容と合格基準
自動車整備士資格の試験内容は、整備技術や知識をしっかりと評価するものになっています。
試験では、エンジンやブレーキ、サスペンションなど、車の各パーツの仕組みや整備方法に関する問題が出題されます。
以下に関する問題があります。
- 構造、機能及び取扱い法に関する一般知識
- 点検、修理、調整及び完成検査の方法
- 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識
- 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識
- 図面に関する初等知識
- 保安基準その他の自動車の整備に関する法規
さらに実技試験では、以下の内容があります。
- 基本工作
- 点検、分解、組立て、調整及び完成検査
- 修理
- 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い
合格率は80%を超えているので、資格の難易度としては低いものです。しっかりと授業の内容を理解していれば、取得できる資格といえるでしょう。

講習で分からなかったところは講師の方にどんどん聞いていたところです。ほぼ毎回聞いており、きちんと自分が説明できるくらいの理解度を持てるようにしてました。あと講習時間に間に合うように仕事の段取りがつけやすかったのが良かったです。もし講習に遅れたり、出席できなかったりすると確実に置いていかれるので注意していました。

とにかく暗記しなければいけないところ(法規)や計算問題など様々あります。分からない所はしっかり質問をして解決する事が大切です!
自動車整備士資格試験の勉強法

効果的な勉強方法と教材
学校に通っているのであれば、集中して授業の内容を理解しておき、自分で教科書を学ぶようにしましょう。完全に独学の場合には、参考書などを購入して自分で勉強する必要がありますが、学校に通っているなら分からない点があれば講師に質問できます。
別の方法として、整備振興会の講習を受けるというものがあります。働きながら資格取得を目指している人向けのもので、試験に必要な知識を学べるでしょう。
独学で勉強していると、どうしても合格率が低くなる傾向があります。確実に資格を取得して、整備士として働きたいなら試験の面からも養成施設の利用がおすすめです。
養成施設なら学科試験に必要な勉強方法を教えてくれ、必要な教材も用意できるでしょう。

主席合格を狙っていたので常に満点を意識して勉強してました。テストや筆記と実技の1発勝負のテストなので緊張感がありました。周りも自分よりも年上の方が多く、経験豊富そうな人が多かったので負けてられないと思いました。

車の構造や法規に関する勉強がマストになります!実車を見ながら勉強出来る環境があればそれが1番です!私は大学で資格取得に向けて講習があり実車を見ながら勉強する環境がありました!カミタケモータースは多数の有資格者が在籍、オールメーカーの車の整備実績もあり実際に車を見ながらの勉強やフォロー体制もあります!
過去問題の利用方法
自動車整備士資格試験の勉強において、過去問題の活用はとても重要です。というのも、こうした資格試験の問題は、過去問題を解いていくことで、実際の試験の傾向や出題内容を把握できるようになります。
過去問題を解くことで、自分の弱点や不得意な分野を見つけることができるのもメリットです。そうすることで、苦手な分野を重点的に勉強できるでしょう。
さらに、過去問題を解くことで、解答のスピードや正確性を高められます。過去問題は日本自動車整備振興会のサイトで公開されているので、事前にどのような問題が出題されたか確認しておきましょう。
繰り返し解いていき、正答率を高めるなら合格の可能性を高められるでしょう。

検査員の問題はひたすら過去問、テキストを読む事。難しかった事は、法律の改訂もあるので過去問をそのまま覚えるだけでなく改訂した部分を上書きしないといけないことです。
自動車整備士資格取得のメリット

就職・転職における有利性
自動車整備士資格を取得すると、就職や転職の際にメリットがあります。自動車整備士としてのスキルや知識があると、自動車関連の企業や整備工場での就職が有利になります。
自動車産業は常に需要がある分野であり、整備士は欠かせない存在です。無資格で行える整備内容もありますが、資格があるなら整備の幅が広がります。
業務の幅を広げるためにも、有資格者は有利になります。
資格取得によるキャリアアップ
自動車整備士資格を取得すると、キャリアアップにつながることもあります。まずは自動車整備士としてキャリアをスタートさせてから、工場長などを目指すこともできるでしょう。
専門学校の段階で1級整備士を取得しているなら、キャリアアップの機会が広がりますし、2級整備士でも他のキャリアアップの機会はあります。
たとえば、営業職への転職や特殊整備士への転職などです。もしキャリアアップの目的が年収になるなら、営業職へのキャリアアップを目指すことが多くなります。
整備士は車の構造を把握しているので、専門的な知識を用いて説明できるようになります。コミュニケーション能力や交渉力が必要な仕事ですが、個人で成績がよいなら評価されて出世する機会があるでしょう。
自分の望む働き方がどうであれ、自動車に関わる仕事なら整備士の資格はキャリアアップを目指すうえで大切となります。

2級整備士の資格を取得したので、整備主任者となる選択肢も増え、もしも部署異動や自営になったとしても活かせる資格だと思います。今後は検査員や1級整備士を目指して頑張りたいと思っています。
資格保持者の平均年収と待遇
自動車整備士資格を持つと、年収や待遇が向上する傾向があります。資格保持者は、そのスキルや知識を活かして幅広い業務に携わることができるからです。
結果として、高度な技術を持つ整備士は、給与や待遇がよくなります。自動車整備士の平均年収は、一般的には約300万円から500万円程度です。ただし、経験や技術レベル、勤務先の規模や地域によって異なります。
ディーラー勤務であれば、給料は高めとなります。福利厚生や休暇の取得、キャリアアップの機会が増えることがあるでしょう。
自動車整備士のキャリアパス

初級から上級へのステップ
自動車整備士のキャリアパスは、整備士としてのスタートから上級までの段階を踏んで進んでいけます。
まずは基本的な整備作業や部品交換などを担当することが多いでしょう。無資格でのスタートなら単純な作業からスタートします。すでに資格を取得していても、実務でのスキルや経験を積み重ねていくことになるでしょう。
数多くの経験を経て、さまざまなパターンに対応できる整備士として活躍できます。チーフメカニックやサービスマネージャーなどの管理職や指導者として働く可能性もあります。
スキルを高めていくことで、技術のある整備士として働けるでしょう。
企業内でのキャリアパス
企業内ではリーダーシップや管理能力を重視されることもあるので、優秀な整備士はチーフメカニックやサービスマネージャーなどの役職に昇進することも考えられます。
また、自動車メーカーのサービスセンターやディーラーでは、特定の車種やシステムに特化したエキスパートとして活躍するチャンスもあるでしょう。
就職した企業によって異なりますが、企業内でもスキルを高めることでキャリアアップを目指せます。

2級取得により整備主任者になる事が出来ます。工場運営になくてはならない存在です!さらに自動車検査員へのチャレンジも可能になるので更なるステップアップが可能になります!
自動車整備士として働くための実務経験

実務経験の重要性
自動車整備士としての受験資格には、実務経験が含まれています。専門学校を卒業すれば卒業と同時に受験できますが、他の条件の場合には実務経験が求められています。
整備士は知識だけでなく、実際に作業する必要があるので、実務経験は大切なのです。無資格から実務経験の年数をクリアするためには、ガソリン整備士の場合は3級を取得してから3年以上が必要です。
専門学校に通うよりも長い実務経験が求められるので、学校に通って免除される方がスムーズです。
もちろん資格を取得しているとはいえ、実務経験が少ないなら仕事としてさらに覚えることはたくさんあるでしょう。
整備士の資格取得を考えているなら、実務経験が大切ということを覚えておき、必要な過程を選択しましょう。
インターンシップや見習い制度
自動車整備士になるための一歩として、インターンシップや見習い制度を活用できるでしょう。もし働きたい企業がインターンシップを募集しているなら、実際に働いてみて整備士とはどのような仕事なのか体験できます。
自分が整備士に向いているのか分かる機会にもできますね。将来のキャリア選択のために活用するのはおすすめです。

一例ですが、弊社では基本的にはみんなフレンドリーで素直な人間であれば頑張っていればしっかり認められる環境です。
自動車整備士資格と継続した教育
継続教育の重要性
自動車の技術は向上しているので、継続して学び続ける必要があるでしょう。同じ整備士でも新しい技術に対応できなければ、市場に出回っている車の整備ができなくなるからです。
たとえば、ハイブリッドカーは10年前と比較しても一般的になりましたし、BEVも普及するようになりました。
新しい車が登場すれば、対応するために継続して学び続ける必要があるでしょう。
新技術・新知識の習得方法
資格を取得したとしても、実際に現場で仕事をしたり、新しい技術に触れる機会があるなら、新しい技術を習得する必要があります。
整備工場では、先輩整備士たちが教えてくれるので、卒業してからも新しい知識を取り入れ続けましょう。ハイブリッドや電動自動車に関する技術は、習得できるなら早く取り入れるのがおすすめです。
自動車整備士に関するよくある質問
- 車の整備には自動車整備士の資格が必要?
-
整備したり、担当できる範囲によって整備士の資格が異なっています。
- どのように整備士の資格を取得するのがおすすめ?
-
専門学校や大学に進学して2級整備士を取得するのがおすすめです。分からないことがあるなら、講師に積極的に質問すると授業について行きやすくなり、合格へ近づくでしょう。
- 整備士のキャリアパスは?
-
検査員や1級整備士を目指すことができるでしょう。部署移動や他の職業に転職する際にも、整備士の資格を活かせます。
まとめ
自動車整備士は、車の整備に関わる仕事を行うなら取っておきたい資格です。専門学校や大学に通って2級整備士を取得するのが一般的で、実務経験を重ねるとキャリアパスも想定です。
車は生活に必要なものなので、整備士はこれからも重要度が高い仕事といえるでしょう。
\新車2.99%の超低金利プランについてはこちら /
カミタケモータース公式サイト


